
「倉庫管理を効率化したいけれど、どの物流パレットを選べばいいのかわからない」
「現在の倉庫で使っているパレットが劣化してきたので、新しく購入するにあたり、別の種類も検討してみたい」
このようなお悩みはありませんか?
この記事では、パレットの種類や、どのような基準で使用するパレットを決定すればよいかなどについて解説しています。読んで頂くことで、パレットに関する理解が深まり、自社の業務に活かすことができます。

私も毎日倉庫でパレットを取り扱っていますので、実体験交えた情報をお届けします。
それではさっそく見ていきましょう!
パレットの種類や形状
パレットには、素材や形状で様々な種類が存在しています。特に、素材によって特徴が大きく異なりますので、これらについて詳しく解説していきます。
木製パレット

木をくみ上げて作ったパレットです。一般的によく見かけるタイプであり、流通量も多いです。木製パレットは、安価で廃棄もしやすく環境に優しい点が特徴です。小さな商品を大量に取り扱ったりする場合は木製パレットは相性がよいでしょう。
ただ、木製パレットは、木なので木屑が必ず発生します。従って、何かの精密機械を取り扱っている会社や、包装をしていない商品などを取り扱っている会社での利用は控えたほうがよいです。(屑が商品に混入し、故障が発生したりと、販売後のクレームリスクなどもあります)
また、木の板を等間隔に組み合わせたすのこのような形状となっている事が多いので、あまりに小さな商品なども載せるのが難しいです。食料品や飲料水などの、段ボール包装された商品の保管や輸送に向いているでしょう。
鉄製パレット

鉄製パレットは、鉄なので堅牢性に優れており、劣化により廃棄する事が少ないです。ただ一方で、単価としては紹介しているパレットの中で一番高額にはなります。鉄製パレットは、その堅牢さを活かして、倉庫内の保管効率を上げる為に利用されるケースが多いです。重量がある商品を、少ないスペースで保管する場合には向いています。

鉄製パレットは、土台の他に支柱がついた立体的な形状になっている事が多いです。高く積み重ねて保管しても、重量により保管物が倒壊したりする心配がないので、商品との相性次第で保管効率を上げることができます。
また、小さく包んだり包装がしにくい商品などを輸送する際にも非常に役立ちます。
例えば、ガラスのような板状の包装できないような物などです。ガラスなので直にトラックへ乗せれば傷がつきますし、板状なので輸送効率も非常に悪いです。このような商品については、ガラス版を囲えるようなサイズの鉄製パレットを制作し、パレットへ差し立てて積載・輸送すれば傷をつけることなく、効率よく運べます。
樹脂製パレット

樹脂製パレットは、鉄製と木製の中間のような用途として利用することができます。樹脂製パレットは、ほかの材質よりは比較的軽く、屑なども出ない為、様々な商品の積載・輸送に利用することができます。単価はバラつきがあり、樹脂量により耐久性や価格が大きく変動します。
樹脂製パレットは、汎用性が高い一方で、気温により変形するリスクがあります。樹脂なので、夏期の気温が高い状態では、柔らかく変形しやすくなり、冬期は乾燥により割れやすくなる傾向があります。
倉庫・物流業でパレットを利用するメリット
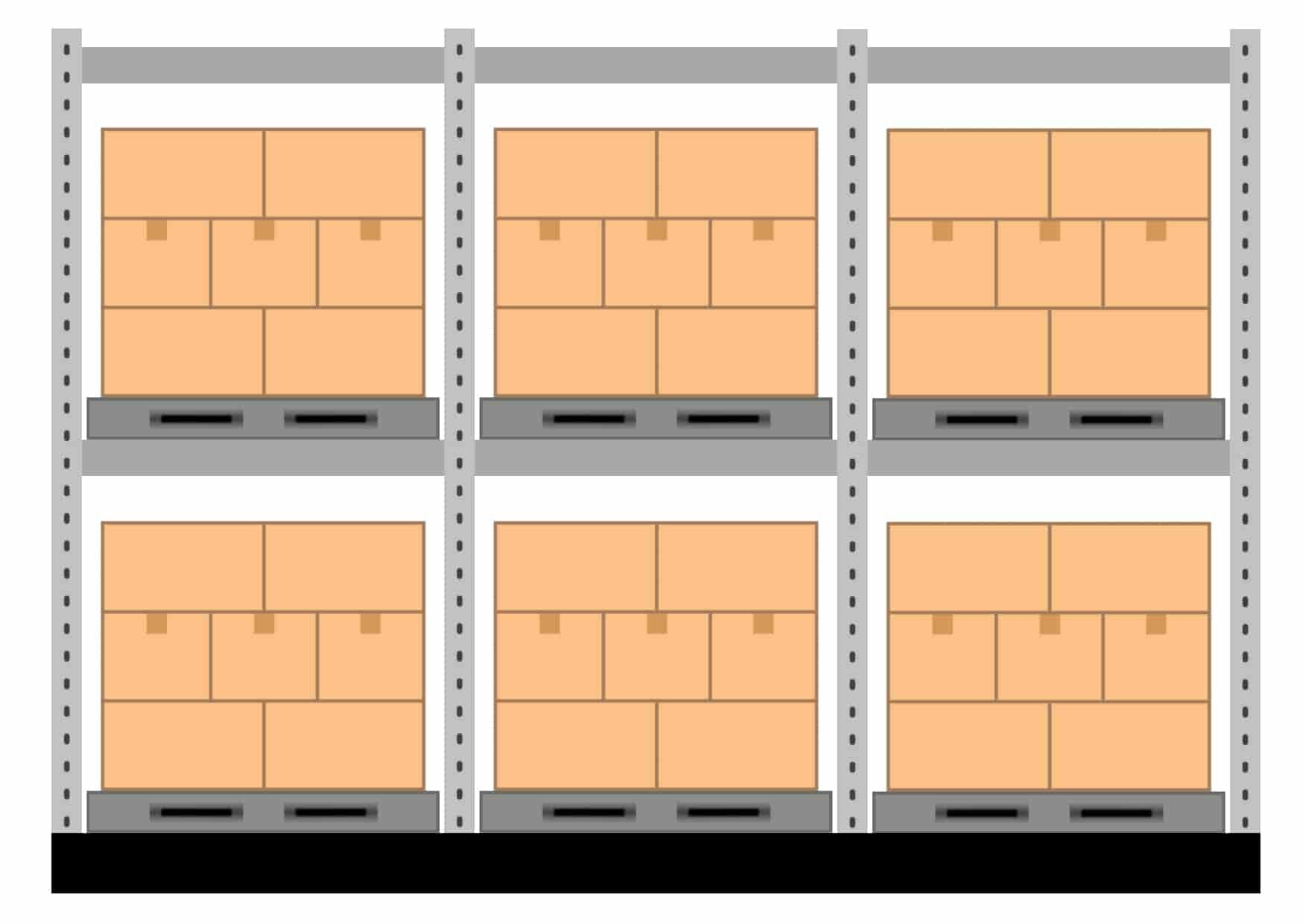
作業を効率化できる
パレットは、小さな荷物を一度に大量に積みつけたり、手では運搬が難しい形状・大きさの荷物をまとめる事ができます。
保管・運搬共に倉庫で発生する主要業務をまとめて行うことが出来る為、大幅な効率化が図れます。また、自社でパレット単位で在庫を管理するシステムなども構築すれば、在庫管理や生産指示といった事務オペレーションも減らすことができ、パレットを利用する事のメリットがさらに増します。
保管効率を向上することができる
パレットを利用することで、商品単体では積み重ねて保管することが出来なかった荷物を、高く積み重ねて少ないスペースで保管を行うことができるようになります。
倉庫業を運営する上で、倉庫の賃料やスペース代は固定費の要になります。使い方次第でこれらの運営コストを大幅に下げることが出来る為、パレットを使用することによる効率向上はメリットとして非常に大きいといえます。

取り扱っている荷物により、どのパレットを使うかで保管効率が大きく変わります。パレットの選定はこのあたりを考慮しながら行うとよいでしょう。
パレットの調達方法

購入
樹脂や木製などの流通量の多い素材・規格のパレットであれば、ホームセンターやECサイトで購入することが可能です。ただ、倉庫を運営されている方などは、大量ロットでの購入が必要になると思いますので、そのような場合は、パレット製造の専門業者へ問い合わせて購入検討するとよいでしょう。
また製造業者へ生産を依頼する場合は、自社の希望に合わせた形状・素材も検討出来ます。特注品を導入して倉庫内の生産性を高める必要がある場合などは、専門の業者で購入するのがよいでしょう。
レンタル
パレットはレンタルすることもできます。一定のロットをレンタルし、月額で利用するというようなイメージです。(料金形態はレンタル会社により異なります)レンタルは、名前の通り自社資産にならない点がメリットで、一定期間利用して返却するといった事ができます。また、パレットは大量購入するとかなり高額になります。まとまったキャッシュの準備が難しいケースなどもレンタルを活用するのがよいでしょう。
ただ、レンタルの場合は、返却しなければならない為、失くさないように管理する必要があります。長距離のお客様への商品輸送や、BtoBの企業などは、パレットだけが企業を跨いで移動し、どこへ行ったのかわからなくなるケースもあります。レンタルを利用するかどうかは、このような業務特性も考慮して検討するとよいでしょう。

レンタル業者によりますが、紛失枚数に応じて追加費用が発生する場合もありますので、レンタルが最終的にコストメリットがあるのかは考えておいたほうがよいでしょう。
パレットを利用・管理する際の注意点
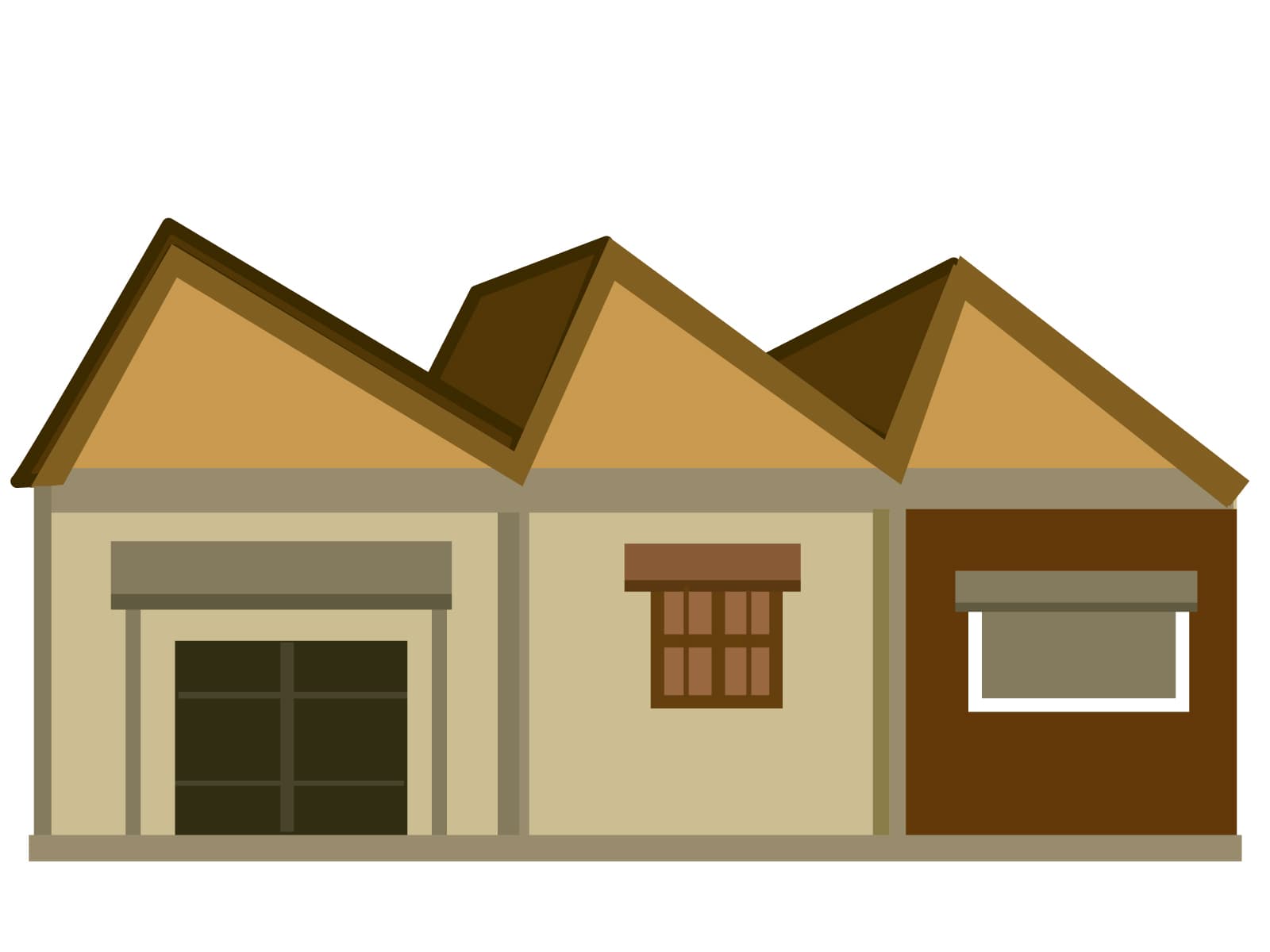
ランニングコストがかかる(紛失・劣化)
一見、パレットは一度購入すればある程度の期間利用できると思われがちですが、実はそうでもありません。短い期間で紛失したり、割れや破損で使えなくなる場合も少なくありません。
前述のとおり、輸送に利用する場合は、ルートによっては紛失しやすかったり、素材によって消耗度合も異なります。購入後は減少率を見ながら追加補充というように、一定のランニングコストが必要になることを頭に入れておきましょう。
防火管理(樹脂製を大量に取り扱う場合)
特に樹脂などの可燃物に該当する素材をパレットとして利用する場合は、防火管理に注意しましょう。パレットは未使用時は大量に一か所へ保管することになるかと思いますが、その箇所は火災リスクが非常に高いといえます。
保管場所の指定や届け出も必要になりますので、これから倉庫業をしていて、パレットの購入が必要な管理職や経営者の方は、これら法規への準拠も注意しましょう。
パレット選定時のポイント

ランニングコストの算出
前述したとおり、パレットは用途によって紛失や破損による消耗が必ず発生します。倉庫経営をされている方や物流倉庫の管理職の方は、これらの予算繰りについても想定しておきましょう。

パレットは、同じ用途、同じ輸送区間などで利用する場合は、ある程度同じ割合で消耗したり紛失をします。利用状況を調査し、減少率分の購入経費を想定しておきましょう。
また、パレットは、ICタグなどを利用して、各個体を追跡することが出来るツールなどもあります。もし導入後に大量にパレットが紛失してしまい、補充コストが高額になってしまう場合などは、これらを検討してみるのも一つです。
自動機との適合性
会社によっては、パレットを平置き・段積保管に利用する以外にも、パレットごと自動ラックのような機械に入れる場合もあると思います。そのような機械を利用されている場合は、機械に投入できる外寸なども事前に確認しておく必要があります。

パレットを購入したはいいけど、社内の設備の規格と合わないから使えないなどの問題が発生すると大変です。事前に調べておきましょう。
輸送トラックへの積載効率
自動設備と同様に、購入するパレットの規格を検討する際には、輸送トラックとの相性も考えておきましょう。保管には効率がいいが、トラックの外寸には全く合わず、輸送コストが跳ね上がってしまうケースもあり得ます。
パレットは、荷物との相性だけで規格を考えず、輸送途上のコストにも目を向けながら最適なパレットを検討しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
パレットは倉庫業・物流において効率化を測ったり、経営コストを下げる為の大切なツールです。ただ一方で、自社のニーズに合わないパレットを選定してしまうと、逆にマイナスコストが発生してしまうリスクもあります。記事に書いているようなポイントに注意しながら、パレットの選定を行ってみましょう。